7月6日(土)、酷暑とその後、激しい雷雨の中、東京・早稲田大学で開催された第60回諜報研究会に参加して来ました。対面とオンラインのハイブリッド方式でしたが、会場に参加されたのはわずか数人と寂しい限りでした。M君も参加すると言ってたのになあ~。ま、雷雨を予想して避けたのでしょう。
山本耕氏「プランゲ文庫所蔵資料などでたどる戦後岐阜」
2人の講師が登壇しましたが、第60回研究会の共通テーマは「占領・冷戦期の知識人・ジャーナリストの行動規制」でした。最初に登壇したのは岐阜放送社長の山本耕氏で、演題は「プランゲ文庫所蔵資料などでたどる戦後岐阜」でした。研究会で現役の社長さんが、登壇するのは今回が初めてではないでしょうか? とはいえ、山本社長は岐阜市出身で、早大卒後、地元岐阜新聞の記者となり、編集局長等も務めたジャーナリストでした。今回は、山本氏が岐阜新聞に約2年半連載した記事を書籍化した「復興期の新聞群像 メディアでたどる戦後岐阜」(岐阜新聞社、2024年5月25日初版)を中心にお話されていました。
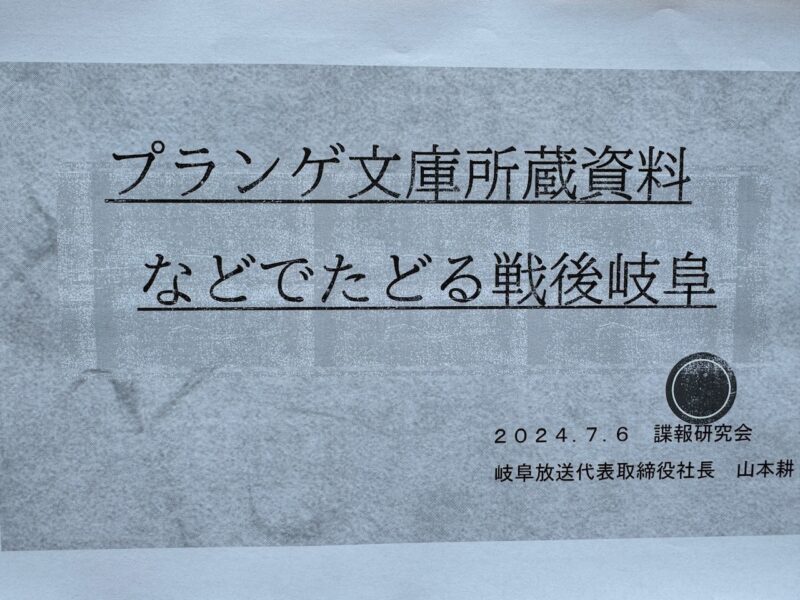
私自身はこの本を読んでおりませんが、明治に創刊された岐阜県紙(明治14年創刊の「岐阜日日新聞」=改進党系、明治21年創刊の「濃飛新聞」=自由党系)に始まり、戦後の占領期の言論統制から解放されたある程度自由な時期に発行された新聞や雑誌などを米プランゲ文庫の目録などを参照して埋もれた歴史を発掘した労作です。
お話はかなり広範囲に渡りましたが、私が独断と偏見で印象に残ったことだけしかここには書けないことをお断りしておきます。まず1人、岐阜県に反骨のジャーナリスト小木曽旭晃(おぎそ・きょくこう、1882~1973年)という人がいたことを初めて知りました。小木曽は、昭和2年から約15年間、岐阜日日新聞の編集局長などを務めた人でした。小学生の時に全聾となり、独学で文学を志し、筆談で会話したことから「逆境の文人」とも呼ばれました。軍国主義という時代背景で、大本営の発表をそのまま垂れ流す全国紙に対する不信感の中、小木曽は「地方が発展してこそ文化国家が成立する」という信念で読者に発信し続けたといいます。
もう一人、岐阜県出身の異色な人物として石神安雄という人がいます。大正3年生まれで、小学校卒業後、岐阜市に出て大手書店で修行し、23歳で独立します。戦中は「愛国百人一首解釈」など戦意高揚の時流に沿ったものを次々と出版し、戦後の昭和22年には、阿部定事件を題材にした「お定色ざんげ」を出版し、阿部定側から名誉棄損で告訴をされると、これを逆手に取って「炎上商法」で5万部も売り上げたといいます。著者の木村一郎の本名は日吉春雄で、東京で印刷工だった頃、労働運動の「北風会」に参加して、大杉栄とも交流があった人だといいます。
この軟派路線に気を良くしたのか、石神は「猟奇」「艶麗」「抱擁」などいわゆる「カストリ雑誌」を次々と発刊し、「岐阜もの」と呼ばれるほどカストリ雑誌のメッカになったそうです。「岐阜もの」ですか?はい、飛騨高山出身の斎藤さんは御存知でしょうが、私は興味がないので、知らなかったなあ~。財を成した石神は、東京・神田須田町に「石神会館」などを開業したほどですから、当時は、石神書店を知らない人はいないぐらいだったのではないでしょうか。
このほか、山本氏は、新聞発行部数の減少に歯止めが掛からない昨今、岐阜県では依然として頑張っているローカル紙があり、特に生活情報に徹する「高山市民時報」や、地域の課題に積極的に提言する「東濃新報」を取り上げていました。
山本武利氏「社会心理学者南博の1952年の中国訪問」
次に登壇したのは、インテリジェンス研究所理事長の山本武利早稲田大学・一橋大学名誉教授で、演題は「社会心理学者南博の1952年の中国訪問」でした。これは、昨年10月に開催された第53回諜報研究会での山本氏による講演の「続編」でした。
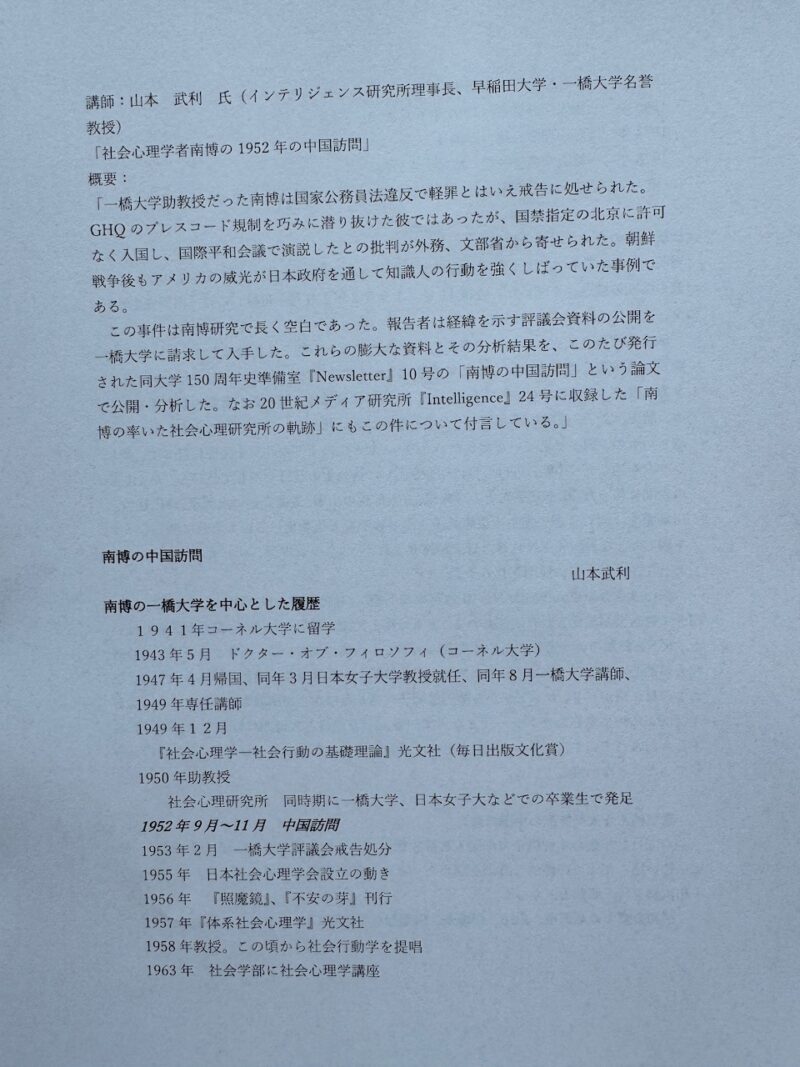
山本氏の学生時代の恩師でもある社会心理学者の南博は、一橋大学助教授だった1952年9月に、突如、当時渡航を禁止されていた中国を訪問し、同年10月に北京で開催された国際平和会議で演説したことから、国家公務員法違反で戒告に処せられました。この事件は南博研究で長く空白、つまり謎に包まれていたので、山本氏はその経緯を記す一橋大学評議会の資料の公開を同大学に請求して入手し、今回の報告に至ったというものです。
確かに、最近、とみに向上していると言われるウィキペディアの「南博」の項目では、この1952年10月の北京演説事件に関して、「空白」になっていますね。
山本氏による請求で公開された一橋大学評議会の議事録によると、1953年2月9日に南助教授の処分に関して評議会が開催され、経過説明の後、国家公務員法第82条に規定する処置として出席者15人による投票を行い、減給を可とするもの7票、減給を否とするもの8票で、辛うじて減給が否定されたことから、戒告処分となったといいます。この時、減給するべきだと演説したのが、サムエルソンの「経済学」などの翻訳で知られる高名な経済学者都留重人教授で、中山伊知郎学長も減給派でしたが、社会学部長の上原専禄教授らが減給に反対(評議会は欠席)していたことなどが分かりました。
何故、都留重人が減給演説をするほど強硬派だったのか、諸説あり、決定的な資料がまだ見つかっていないので真相は不明ですが、学内で誰が実権を握るか内部闘争の意味合いもあったようです。報告者の山本氏も「都留提案が可決されれば、社会学部の反発で学内分裂という薄氷の裁決だった」と分析しておりました。
南助教授が中国を電撃訪問した1952年は、その年の4月28日まで、日本は米軍(GHQ)による占領下だった時代背景を忘れてはいけません。それに、朝鮮戦争(1950年6月25日~1953年7月27日)がまだ続いていた年でもあり、中国八路軍も参戦し、米軍と対峙していた時期ですから、南助教授の訪中がいかに国際政治に波紋を投げかけたか、かなり衝撃的で、新聞(特に読売新聞)も詳細に報じました。
それにしても、何故、南博は訪中したのか? 南博は、1952年8月、ユネスコ主催でパリで開催された「国際社会心理学会」に参加した後、真っ直ぐに帰国せず、ドイツ、ソ連を経て中国入りしたといいます。理由について、明確な資料は見つかっていないのですが、これだけ大掛かりな旅行ですから、事前にかなり入念に計画が立てられたことは確実です。報告者の山本氏は、背後に中国(共産党政権)と国交を回復しようとするグループがいてそのバックアップがあったのではないか、と推測しています。そのグループの主要人物として、早大教授から衆院議員などを歴任した大山郁夫がいたのではないか、とまた推測しています。確かな資料が出て来ないので、推測の域は出ませんが、南博の母親と大山郁夫の妻は大阪の女学校時代の親友だったことから、南博と大山郁夫と面識があったからだといいます。
南博は大学での戒告処分を受けた後、「中国 ヨーロッパを追い越すもの」(光文社、1953年)を出版し、毛沢東率いる中国共産党政権についてかなり好意的に書いています。この点について、報告者の山本氏は、米国人ジャーナリストのエドガー・スノーが毛沢東にいわば洗脳されたかのように、中国共産党に対して好意的な「中国の赤い星」を書いたように、若い南助教授もそんな役割を担わされたのではないか、とまたまた推測していました。
その後の毛沢東による大躍進運動や文化大革命によって、何百万人、何千万人もの中国人民が犠牲になった歴史的事実を見るにつけ、その推測は的外れではなく、かなり事実に近いと私も思います。
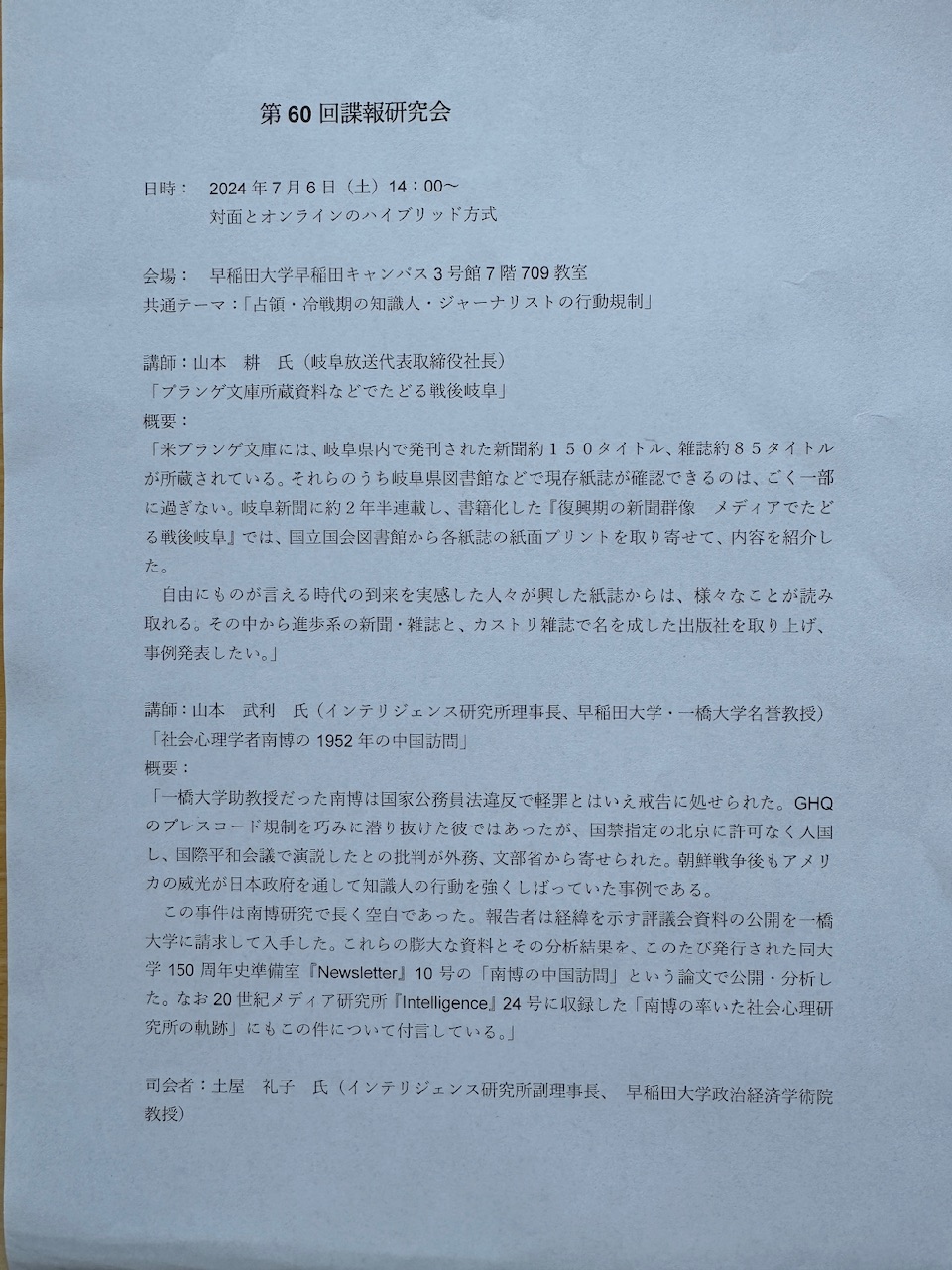


コメント