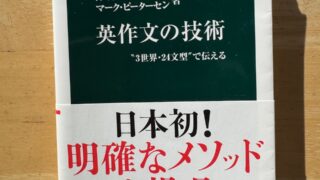 書評
書評 ネイティブも苦労して覚えている? 澤井康佑、マーク・ピーターセン著「英作文の技術」
英語は覇権主義国家米国の影響で、最も汎用性の高い言語ではありますが、修得するには最も難しい言語ではないでしょうか。特に日本人にとって。むしろ、漢字文化圏に取り込まれているので中国語の方が優しいのでは? 何故、日本人にとって英語が難しいのかと...
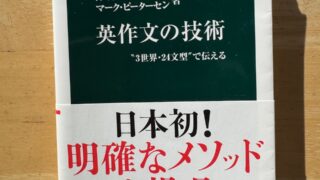 書評
書評 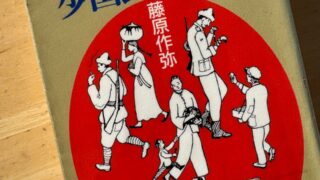 書評
書評 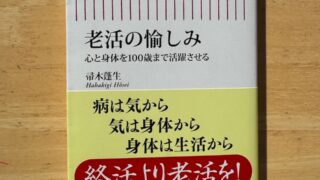 書評
書評 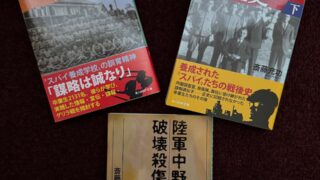 書評
書評 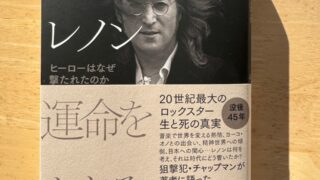 書評
書評  書評
書評 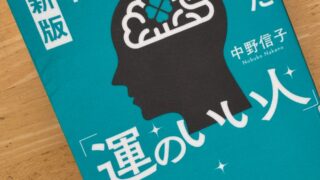 書評
書評 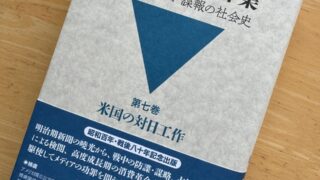 書評
書評 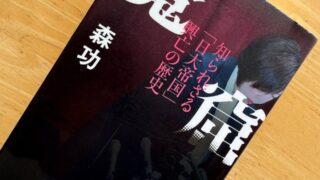 書評
書評  書評
書評