4月19日(土)、東京・早稲田大学で開催された第65回諜報研究会に参加して来ました。この日は、JR東日本の山手線と京浜東北線が工事のため一部路線で運行停止だったため、わざわざ普段とは違う路線に迂回して早めに早稲田にまで行ったので大変苦労しました。自宅で悠々とオンライン参加とは違います、と皮肉を書いておきます。
最初に断っておきますが、私は諜報研究会の公式記録員ではありませんから、研究会に対して耳が痛くなるような批判も書きます。また、講師や質問者に対してもあまり好意的でないことも書きますが、これはあくまでも個人の見解、もしくは暴論であって、諜報研究会の公式見解ではないということです(断るまでもないかあ~)。
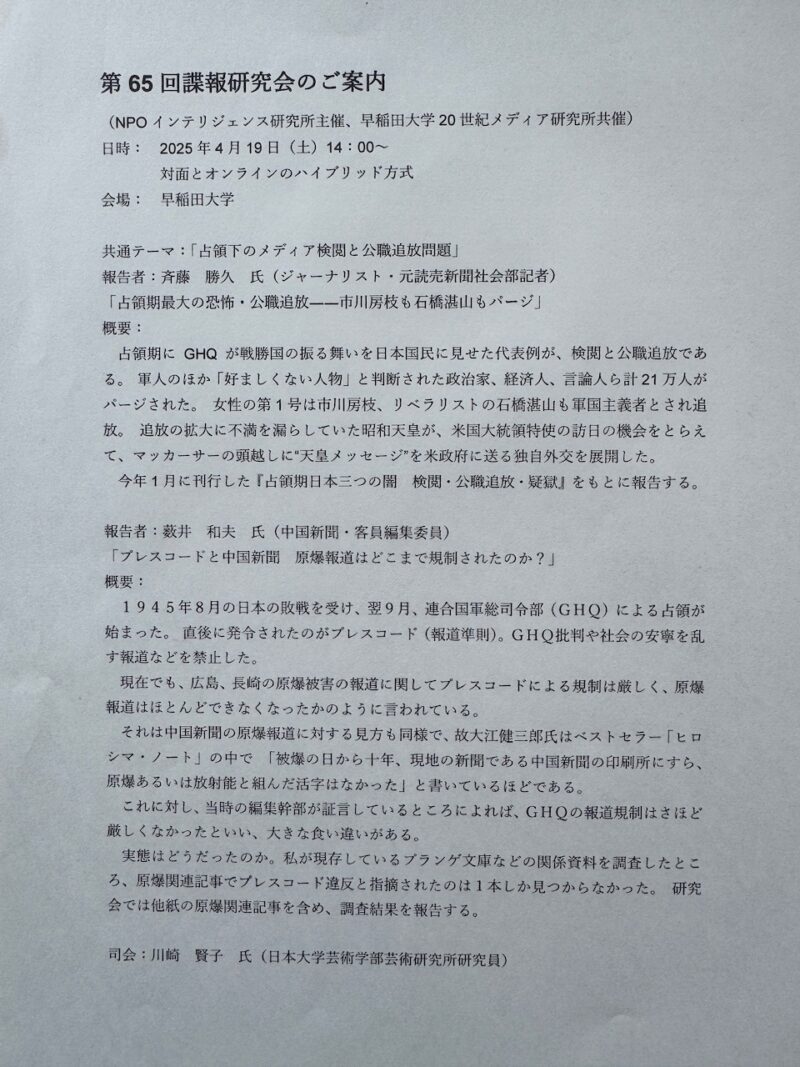
第65回諜報研究会(随分、長く続いているものです。正田事務局長の無償奉仕の賜物です)の共通テーマは「占領下のメディア検閲と公職追放問題」でした。興味深いテーマのせいだったのか、会場には19人参加し、オンラインでは約50人も参加されたようです。前回の会場参加は数人で、関係者を除くと私1人ぐらいでしたので、えらい違いです(苦笑)。
「プレスコードと中国新聞 原爆報道はどこまで規制されたのか?」
最初の報告者は、中国新聞客員編集委員の薮井和夫氏で、テーマは「プレスコードと中国新聞 原爆報道はどこまで規制されたのか?」でした。薮井氏は、オンライン参加でした。中国新聞ですから、恐らく、広島市在住の方と思われますが、会場で直接、お話したかったと思いました。
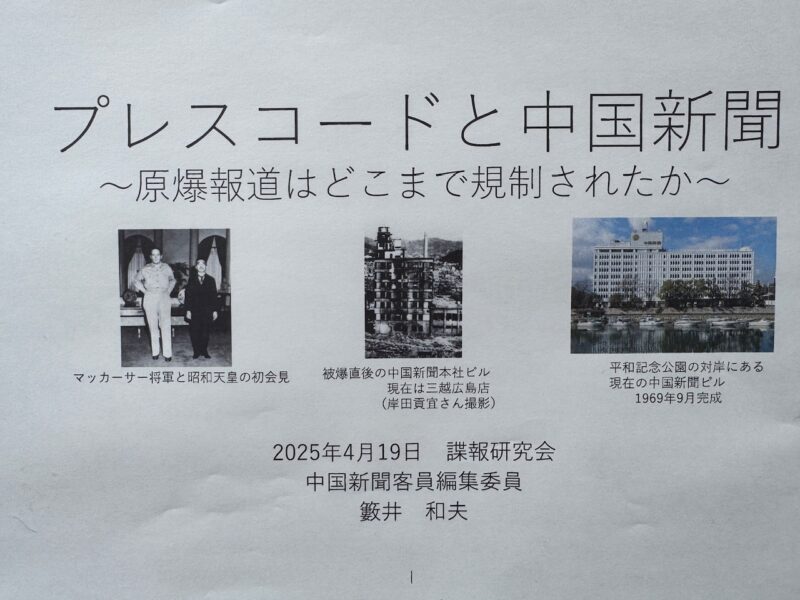
1945年8月の日本の敗戦で連合国軍総司令部(GHQ)による占領が始まり、GHQは、批判や社会の安寧を乱す報道などを禁止するためにプレスコード(報道準則)が発令しました。これによって、広島、長崎の原爆被害の報道規制が厳しく、「原爆報道はほとんど出来なかった」と定説として言われてきましたが、それは本当なのか? と薮井氏がジャーナリスト特有の臭覚で自社の中国新聞の当時の報道を調査した報告でした。
私も質問というか、確認がしたかったのですが、オンラインで三つも四つも質問する人がいて、めげてしまって時間もなくなり質問が出来なかったのですが、占領期当時(1945~52年)の中国新聞の原本はどういう理由か分かりませんが、残っていないと思われます。そこで、薮井氏は、「20世紀メディア情報データベース」に登録されている中国新聞9万7613本(1946年3月24日~49年10月13日)と同社の関連会社が創刊した夕刊ひろしまの記事やプランゲ文庫の関係資料も調べたところ、掲載された原爆記事は1505本もあったといいます。そのうち検閲の対象になった記事は679本で、プレスコード違反になった記事はわずか1本しか見つからなかったといいます。ただし、中国新聞の1947年はほとんど欠落していて1カ月分しか残っていなかったので、薮井氏は、1本と結論付けることにかなり悩んだそうです。しかしながら、「中国新聞が原爆報道を出来なかった」という定説はフェイクだったという確証をつかめたわけです。
ですから、ノーベル賞作家大江健三郎氏が、ベストセラーになった「ヒロシマ・ノート」(岩波新書)の中で 「被爆の日から十年、現地の新聞である中国新聞の印刷所にすら、原爆あるいは放射能と組んだ活字はなかった」といった記述は大間違いだったということになります。薮井氏は、版元の岩波書店に訂正を申し入れしたそうです。(ただし、中国新聞社として正式に抗議したわけではなく、大江氏も故人であり、記述はそのままになっているようです)
これらについて、薮井氏は、自身が所属する中国新聞社の定年を延長して、2023~24年にかけて「ヒロシマの空白 中国新聞とプレスコード」と題して長期連載しました。そしたら、報告が終わった後の質問コーナーで、ある人が「プレスコード違反という設問自体に違和感があった。プレスコードは表向きの話で、検閲そのものが問題であって、見方が甘いのではないか」と仰るのです。その人は「失礼ですが」と付け加えておりましたが、確かに随分失礼な質問をズケズケとする人だなあと私は思いました。詰問された薮井氏は答えに窮したのか、無言のままでした。そりゃあそうでしょうね。薮井氏は、労苦を全否定されたわけですから。
「占領期最大の恐怖・公職追放――市川房枝も石橋湛山もパージ」
次に会場参加で登壇されたのが、元読売新聞社会部記者でジャーナリストの斉藤勝久氏で、テーマは「占領期最大の恐怖・公職追放――市川房枝も石橋湛山もパージ」でした。
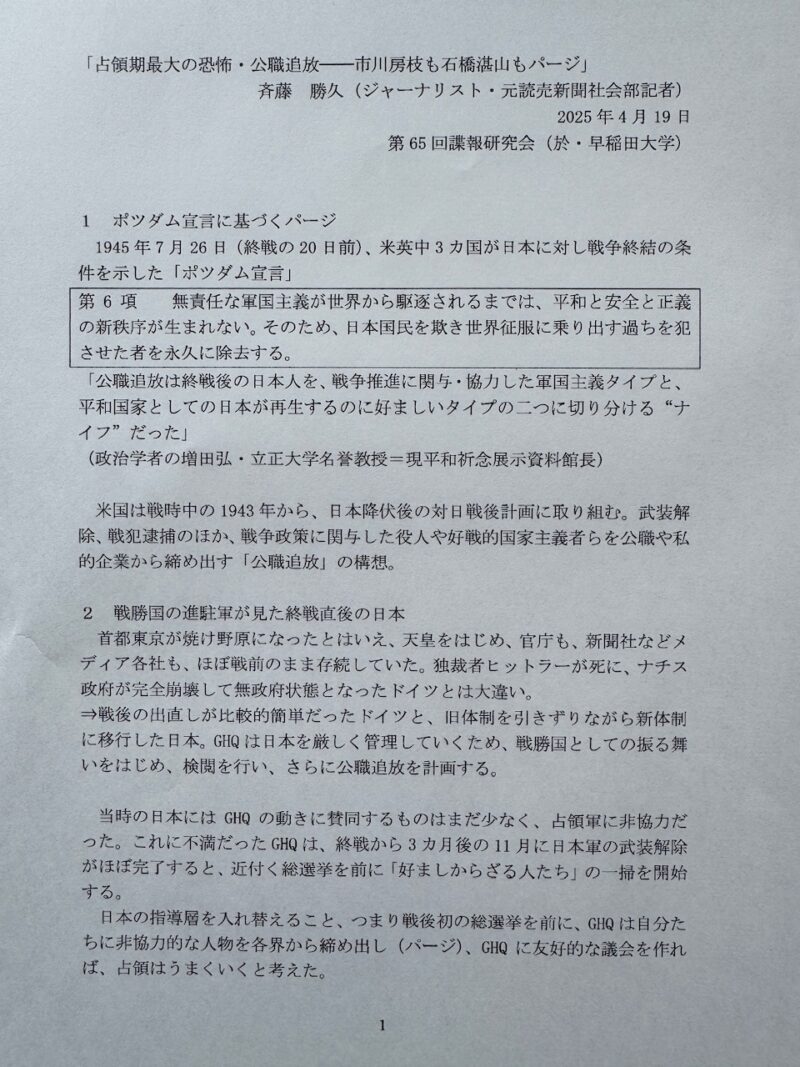
斎藤氏は今年1月、「占領期日本三つの闇 検閲・公職追放・疑獄」(幻冬舎新書)を刊行しましたが、この三つの闇の中の一つである「公職追放」に絞った報告でした。
1946年1月、GHQは、ポツダム宣言第6項に基づき、いきなり「公職追放」を実行します。その内訳は、 軍人(79.6%)のほか「好ましくない人物」と判断された政治家(16.5%)、超国家主義者(1.6%)、官僚(0.9%)、経済人(0.9%)、言論報道関係者(0.5%)の計21万288人でした。 そのパージ判断基準は実に曖昧というか、いい加減で、女性第1号の市川房枝や石橋湛山らリベラリストだけでなく、次期首相候補だった鳩山一郎まで追放されるほど恣意的でした。こういった追放の拡大に不満を募らした昭和天皇が、アイゼンハワー米大統領特使、ダレス国務長官の訪日の機会をとらえて、GHQマッカーサーの頭越しに「天皇メッセージ」を米政府に送る独自外交を展開した秘話まで披露しておりました。
もう少し、詳しい内容が知りたかったのですが、時間切れで途中で終わってしまった感じでした。そこで、会場で、斎藤氏の新著「占領期日本三つの闇 検閲・公職追放・疑獄」が即席販売されていたので、早速購入致しました。この本の感想文について、またいつか、このブログに書きたいのですが、何しろ目下、無暗に購入してしまった本が、私の書斎の机の上に富士山ぐらいの高さで、「積読状態」になっておりますので、果たしていつのことになるやら…。



コメント