本日は、「満蒙開拓、夢はるかなり」「昭和解体」「暴君」「転生」など多数のノンフィクション作品を発表し、今年1月には最新作「成田の乱」(日本経済新聞出版)を上梓された牧久さんと久し振りに東京・内幸町の日本記者クラブのラウンジでお会いし、懇談しました。前回お会いしたのがいつだったのか覚えていませんが、多分、十数年ぶりです。本の著者略歴で紹介されている通り、牧さんは1941年生まれですから、今年84歳です。いまだにバイタリティーに溢れ、現役のジャーナリストとして活躍されているので、頭が下がるばかりです。
手紙と葉書でやり取り
今回、お会いするに当たって苦労したのは、連絡方法です。牧さんは、パソコンはタイプライター代わりには使うそうですが、インターネットもメールもやめてしまったからです。理由は、ネット上の過激なフェイクニュースや迷惑メールが多過ぎて嫌になったから、と言いますから、大変理にかなっています。そのせいか、いまだに紙の本に拘っているわけです。
電話もありますが、結構繋がらなかったりしましたので、結局、私も手紙と葉書というオールドメディアを使って、牧さんとの面会に漕ぎつけました。昔はそれが普通でしたからね(笑)。世の中、これだけスマホが普及しても、「携帯は生涯持たない」と言う芸能人もいるくらいです。だから、ネットをやらなくても別にいいじゃありませんか。投資詐欺や国際ロマンス詐欺の術中にはまる危険性も減り、AIによって振り回されずに済むかもしれません。
情報の遮断も必要
最新作「ネクサス 情報の人類史」を出版したイスラエルのユヴァル・ノア・ハラリさんも最近、恐らく出版社の招きで来日し、日本のメディアの取材を受けていました。彼は「今は情報過多で戸惑う人が多い。他者に左右されず、自分自身で物事を考えるには、たまには情報を遮断することも必要です」といった趣旨の発言をしておりましたが、これもネットやSNS中毒の危険性を指摘したものだと思われます。断捨離じゃありませんが、たまにはYouTubeやFacebookなんか見ないで、ネット情報から離れる勇気を持つことが肝心ですね(笑)。
あれっ?牧さんとの懇談の話でしたのに、あらぬ方向に話が飛んでしまいました。でも、これで良いのです。十数年ぶりにお会いしたので積もりに積もった話で盛り上がりましたが、ほとんどブログには書けないことばかりでした(苦笑)。これは、これまで何回もこのブログで書いて来ましたが、ネットに情報を上げると、タダで情報が吸い上げられてAIによって利用されるだけですからね。
新東京国際空港は木更津にするべきだった?
それでも、警察と学生ら反対派の両方に多数の死者を出した三里塚闘争の「成田の乱」を書いた牧さんのお話で興味深かったことを一つだけ挙げると、新東京国際空港を成田に決定した佐藤栄作首相(当時)の甘い判断が間違っていたということでした。成田には、天皇御用達の「御料牧場」があり、これを何処かに移転すれば、それ以外は、農民たちが簡単に立ち退いてもらえるといった甘い判断です。しかし、御料牧場は、空港用地のわずか4割程度で、残りの6割は耕作農地でした。最初から土地収用は難航することは分かりきっていました。むしろ、河野一郎建設大臣(当時)が推していた千葉県の木更津にしていたら、13年に及ぶ三里塚闘争に発展しなかったというのが牧さんの見立てです。
木更津の空港予定地は埋立地でした。遠浅の海岸だったため、これなら農民を追い出して土地を確保する必要はありません。ただし、当時(1964年)は、空港用地を確保できるほど広大な埋立地をつくる技術と予算の関係と地元の反対で断念したようです。それに、木更津から東京へのアクセスの悪さが一番の問題になりました。しかし、その後、木更津と川崎を結ぶ東京湾アクアラインが1997年に完成し、木更津から川崎まで、車で所要時間がわずか15分になりました。となると、アクアラインが開通するかもしれない将来性を見込んで、木更津に新東京国際空港をつくることが出来ていたら、三里塚闘争など起きず、これほどの問題にならなかったという話でした。
牧さんは日経社会部の記者だった20代から現場取材を続け、デモで学生らの投石に当たって大怪我をした経験もあります。それらは「成田の乱」に全て書かれています。現場に立ち合い、半世紀以上に渡って三里塚闘争の行く末を見続けた牧さんは、現在も闘争は続いているとはいえ、一冊本を書いたことで、長年の宿題をやり終えたような感じでした。「警官、学生双方に死者が出て、13年以上続いた成田闘争に関して、これまで一冊もまとまった本が出ていなかった。これをなかったものにしたくなかった」とこの本を書き挙げた動機も語ってくれました。ジャーナリスト魂を見た感じでした。

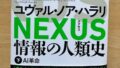

コメント