倉本一宏著「紫式部と藤原道長」(講談社現代新書、2023年9月20日初版)を読み終わりましたが、最後の方は、私自身も、何とも喉がかわいて、病悩でのたうちまわってしまう感慨に襲われてしまいました。
藤原道長の晩年がそうだったからです(藤原実資「小右記」)。日本史上稀に見る最高権力者として32年間君臨して栄華を極めた人ではありますが、その晩年は、病苦の連続で、気を失って前後不覚になることもしばしば。「やたらと喉がかわく」というのは、現代病で言えば、道長は糖尿病に罹っていたのではないかという説が有力です。現代なら良い薬もあるので、症状も和らぎ、62歳の若さで亡くなるようなことはなかったでしょうが、哀れというより惨めというのが晩年の藤原道長の姿でした。
この本で著者が一番言いたかったことは、最高権力者である藤原道長がいたから王朝文化が華開いたというものだったと思います。特に、紫式部は、道長の後ろ盾があったからこそ、「源氏物語」を書き続けることが出来て、その作品を後世に残すことができたわけで、著者の倉本氏も「道長なくして、紫式部なし、紫式部なくして道長なし」とまで書いています。また、続けて「世界最高峰の文学作品と日本史上最高の権力者が、お互いの存在なくしてはあり得なかったということは、歴史上の奇蹟と称すべきことであると同時に、また歴史上の必然でもあったことになる」とまで付け加えております。
この渓流斎ブログで先日もこの本について取り上げましたが、やはり、この本は、目下放送中のNHK大河ドラマの「光る君へ」の鑑賞の手引きになることは間違いありません。
ドラマは、大した戦乱もなく、華やかで美しく、綺麗ではありますが、歴史上の現実は、かなりどす黒い権力闘争が展開し、呪詛したり、されたりの応酬です。後宮では、女房同士でやっかみや足の引っ張り合いがあったことがこの本を読むとよく分かります。ですから、以下の記述を目にした時は、さすがに暗澹たる思いをしました。
いくら「源氏物語」の作者として名声を得てはいても、それが現世での幸福に直接つながるものではなく、まして富や地位をもたらすことはなかった。「源氏物語」の読者も、原本や転写本を借りることのできる階層に限られ、それほど広範に読まれていたわけでもなっかったのである。そして当時は物語よりも和歌の方が価値が高いとされていた。
倉本一宏著「紫式部と藤原道長」(講談社現代新書、2023年9月20日初版)310ページ
その証拠として、藤原氏の筆頭家である近衛家には「源氏物語」の古い写本があったというのに、1467年からの応仁の乱の際、近衛家は、藤原道長の「御堂関白記」などは京都郊外に疎開させたのに、「源氏物語」は洛中の近衛邸に置いたままだったので、戦乱で焼失してしまったといいます。著者の倉本氏も「前近代における文学の地位は、こんなものだったのである」と嘆いております。
諸説ありますが、紫式部の生没年は不明で墓所も分からないというのが歴史学上では正しいとされています。
いずれにせよ、いつの時代も、人間、自分の思い通りに生きることは難しく、栄華を極めたあの藤原道長でさえ、生きている現実は厳しかった、ということをこの本で再認識させられました。
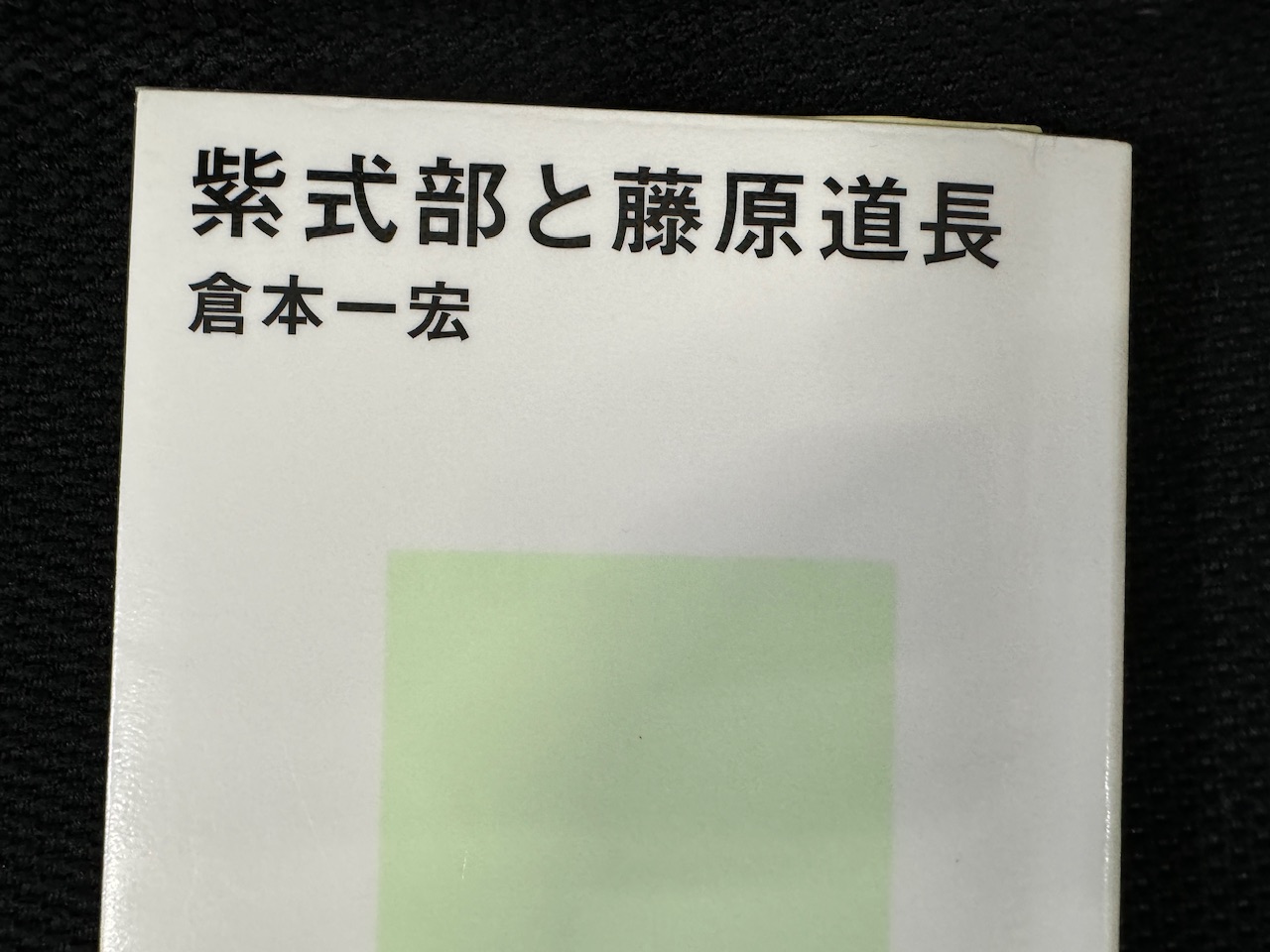



コメント