2016年から22年までの6年半、朝日新聞朝刊一面コラム「天声人語」を執筆していた有田哲文記者(60)の講演会を聴きに行って来ました。新聞業界が斜陽化になった昨今、私がいまだに、毎月4900円も払って朝日新聞を購読しているのは、この天声人語を読みたいがためと言っても過言ではないくらいで、その裏話を聞きたかったからでした。講演会は500人ぐらい参加しましたが、抽選で、私はギリギリ当選しました。
悩める人間
どんなエリート記者が登場するのかと思ったら、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、私とそれ程変わらない、極めて謙虚な「悩める人間」記者でした。上司から天声人語の執筆を打診された時は青天霹靂で、「もっと教養があって、文章が上手い人が書くものだと思っていた」ため、一晩、時間を置いて返事をしたそうです。最初の頃は、なかなか書けずに、週に1回は「どこかに逃げ隠れて消えたい」という失踪願望に駆られたそうです。
有田記者は、エリートと言えばエリートなのですが、最初「女性セブン」の編集者からトラバーユして朝日に途中入社した人でした。天声人語では有名な深代惇郎氏は、東大法学部卒から朝日新聞に入社したエリートでしたから、意外に思えました。
執筆の極意
有田記者は、もう一人の山中(たぶん季広)記者と二人で担当し、土曜日から金曜日までの1週間ずつ交代したそうです。本人は「死のロード」もしくは「南アルプス縦走」と呼んでおりました。1日交代ですと、毎日のプレッシャーで実質的に休養日がなくなってしまうからだそうです。それでも、毎日、「ネタ探し」で呻吟していたそうです。
天声人語は、603文字、6段落という定型が決まっています。まるで俳句や短歌の世界です。歌舞伎の様式美みたいなものです(笑)。執筆に当たって参考にしたのは、米国のコラム二ストや故・小田嶋隆氏、町田康氏らの本で、(1)「そんなこと知らなかった」といった要素を一つ入れる(2)「そんなこと考えたことがなかった」といったアイデアを一つ入れる(3)起承転結は考えない(4)いきなり鳥の目になって高い上から目線で見るのではなく、ビール瓶のケースの高さぐらいに乗って見通しをする(5)自分が本当だと思うことを書くーということだったそうです。
紙の本の世界の奥深さ
有田記者の話で私が一番感動したのは、彼が参照したのは、ネット情報ではなく、書籍だったということです。そのために、会社や自宅近くの図書館5〜6件も登録して通ったといいます。「自分自身のことをネットやAIで検索しても、ネットに拡散された情報しか出てこない。やはり、紙情報の方が、ネットより上です。紙の本の世界の奥深さを痛感しています」というのです。同感ですね。特に私はアナログ人間で、反AI主義者ですからね(笑)。
もう一つ感心したのは、執筆に当たり、上層部から何ら制約を受けずに自由に書けたということでした。ただし、公序良俗に反することや、人を傷つけるようなことを書かないように気をつけたといいます。
最後は興醒め
会場には、「天声人語を半世紀以上愛読している」という人や、「15年前から、『天声人語』の写し書きをしております」という熱心な参加者もおりました。
しかし、講演会の主催が地元販売店や事業部だったようで、最後は「朝日新聞デジタルを月500円で買ってください。本日、契約して頂いた方は、この後、有田記者との懇談会に参加できます」といった長い長い宣伝でした。まあ、タダで講演会を聴きましたが、興醒めしました。
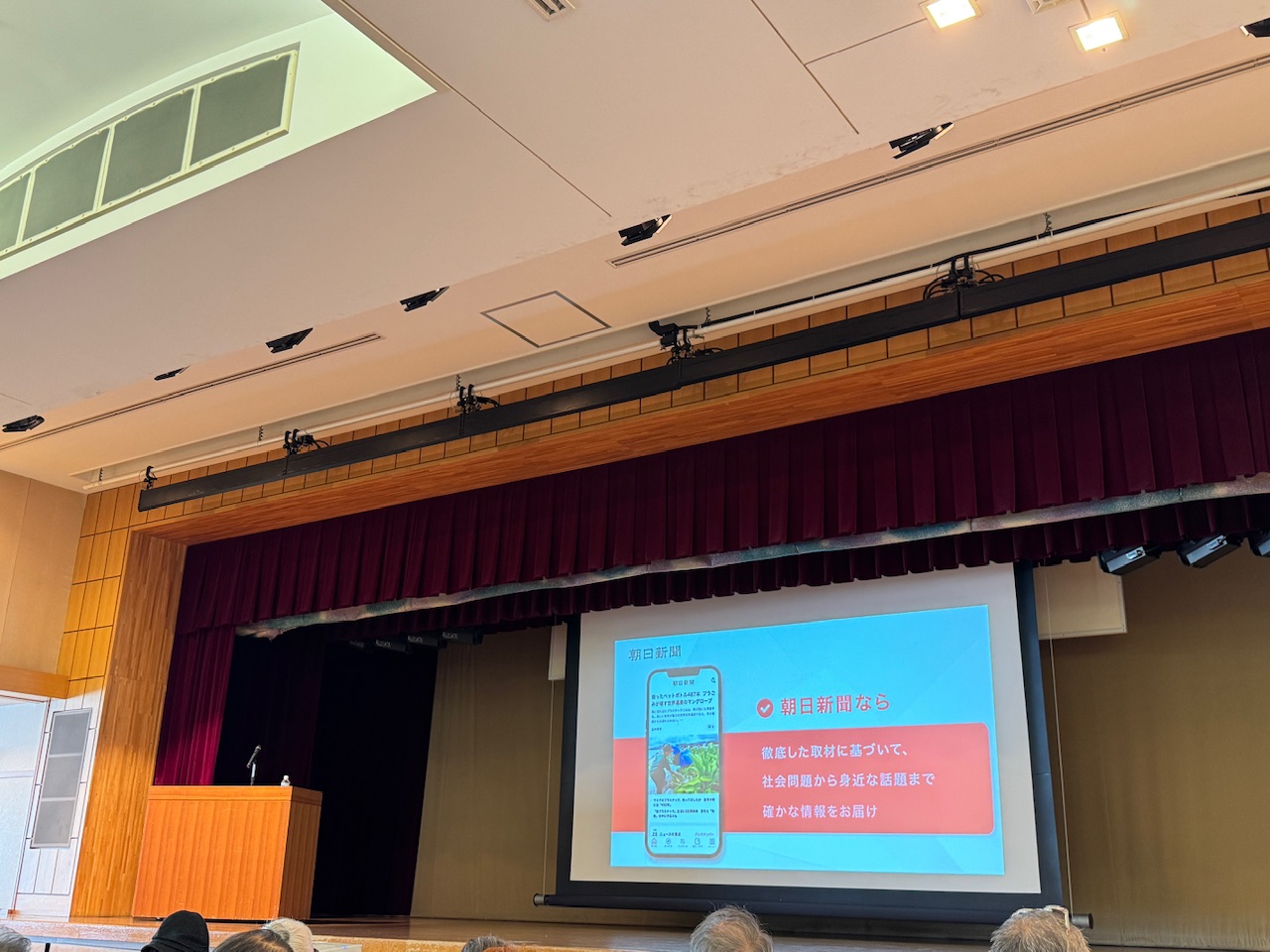


コメント