先日、「武蔵の小京都」と呼ばれている埼玉県比企郡の小川町に行って参りました。電車ですと、東武東上線で池袋から1時間ほど掛かります。私の自宅からは乗り換え、乗り換えで2時間掛かりました。
小川町は知る人ぞ知る歴史のある街ですが、私のように全く知らない人間もおりますから、今、大々的に観光地として売り出しています。
町が売り出すセールスポイントは、三つのユネスコ無形文化遺産があるということです。①和食②酒蔵③細川紙(小川和紙)ーの三つです。
割烹二葉の「忠七めし」
①の和食で1軒だけ例を挙げると、割烹二葉の「忠七めし」があります。幕末の江戸無血開城で貢献した山岡鉄舟が、同店の八代目当主八木忠七に示唆して作らせたという「日本五大名飯」の一つと言われています。山岡鉄舟と小川町との関わりは、もともと鉄舟は、幕臣で御蔵奉行小野高福の五男として生まれましたが、山岡家の養子になりました。小野家の知行地がこの小川町にあったので、鉄舟も度々訪れていたのでした。
この「忠七めし」は、映画監督の黒澤明や脚本家の向田邦子らも好んだそうです。残念ながら今回、私は食しませんでしたが。
埼玉県の地酒生産は全国4位
②の酒蔵は、町内に何軒か造り酒屋があり、予約すれば、見学もさせてくれます。私は、晴雲酒造という所に行ってみました。埼玉県産の日本酒といえば、私は、東京・銀座にも店がある「秩父錦」ぐらいしか知りませんでしたが、実は、埼玉県の地酒は全国で第4位の生産量を誇るんですね。第1位は、「灘の生一本」で有名な兵庫県、第2位は伏見の京都府、第3位は米どころの新潟県です。第5位は秋田県ですから、埼玉県は本当に意外でした。

晴雲酒造では、酒専門用の米「山田錦」などに麹maltを入れて、もろみmashを造り、これを圧縮したり、ろ過したりしてお酒を造る過程を教えてもらいました。作業は、新米が出る9月末から翌年の4月ぐらいまで半年以上掛かるそうです。
酒造りは寒い方が良く、小川町は盆地で冬の寒さが厳しいので酒造りに適しているそうです。何故、寒い方が良いのかというと、暑いともろみが腐ってしまうそうです。だから、暖かい九州の熊本や宮崎、鹿児島などでは、日本酒造りに適さず、焼酎が多いというのです。そっかあ~、長年の謎が解けた感じでした。
風船爆弾にも使われた細川紙
③の小川和紙は、1300年もの歴史がある伝統職人芸です。古代(716年)、武蔵(特に今の埼玉県)には多くの渡来人が移住し、今の飯能市の高麗(高句麗から)や新座(新羅から)などに地名が残っています。小川町にも渡来人が移住し、紙漉きを伝えたという説が有力です。
小川和紙の全盛期は江戸時代で、中でも、ユネスコの無形文化財に指定された細川紙は、大変重宝され、一大消費地・江戸にも舟による流通で近いということで、大量に生産されたといいます。
細川紙は、薄くて大変丈夫だということで、商家の大福帳account bookや障子や襖、また浮世絵にも使われたといいます。

戦時中は、何と、風船爆弾にも使用されたと聞いて驚きました。
今では、経済原理によって、さすがに産業としては廃れてしまいましたが、現在でも稼働している製紙工房が何軒かあり、古典の書籍や絵画などの修復用紙や、行灯、名刺、葉書、便箋、封筒、工芸品など幅広く使われています。
小川町発祥の「ヤオコー」と「しまむら」
あと、忘れてはならないのは、小川町を発祥の地としているのが、スーパーマーケットのヤオコーとファッションセンターのしまむらです。
ヤオコーは、明治23年(1890年)に八百幸商店として創業され、今では関東地方を中心に195店舗も展開しています。
しまむらは1953年、島村呉服店として設立され、「しまむら」だけでなく、「アベイル」「バースデイ」などグループで全国2000店舗以上展開しています。
私は今回初めて知りましたが、小川町(現在の人口は2万7000人)は結構、商才がある人を輩出していたのですね。知る人ぞ知る伝統の町「武蔵の小京都」でした。


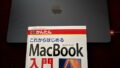
コメント