いやはや、すっげー本をやっと読破できました。ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳「ネクサス 情報の人類史」上下(河出書房新社、2025年3月20日初版)のことです。
2020年代に読んだ本のベストワン
上下巻(4400円)合わせて500ページ以上、原註釈80ページ弱という超大作で、発売日の3月8日から少しずつ読み始めたので20日以上掛かりました。昔、昔の話、私が文藝担当記者だった若き頃は、1カ月に30冊は本を読んでおりましたが、さすがに寄る年波と目元の衰え等もあり、退化してしまいました。読んでいてすぐ雑念に襲われることも原因の一つでした。前回、このブログにも書きましたが、この本は、最初読んでいても、何を書いているのか内容がさっぱり理解出来ず、「著者は一体、何を言いたいのか?」と思ったほどでしたが、上巻の終わり辺りになって、俄然面白くなり、下巻は全て内容も分かり、面白くてたまらなくなりました。ですから、上巻の途中で諦めずに最後まで読み通すことが肝心です(笑)。今のところ、私が2020年代に読んだ本のベストワンと言ってもいいぐらいです(2010年代のベストワンは、同著「サピエンス全史」です)。
人類の情報伝達の歴史
著者のハラリ氏は、技術者ではなく、歴史家なので、内容は、人類の情報伝達の歴史が書かれています。具体的には、税徴収のために考案された古代メソポタミアの楔形文字や聖書やコーランなどを出来るだけ多くの人間に普及するためにも考案された印刷革命、それに付随した魔女狩りや宗教戦争、そして産業革命を経て、新聞、ラジオ、映画、テレビといったメディアが発展し、民主主義や全体主義といった体制に利用され、さらに現在はAI革命が進行中で、将来どうなってしまうのか、著者なりの見通しと言いますか、展望が開陳されます。
ハラリ氏1人で書いたわけではない?
内容については、巻末にある柴田裕之氏による「訳者解説」が非常に分かりやすく、よくまとまっているので、これさえ読めば十分かもしれません。また、繰り返しになりますが、著者は技術者ではなくあくまでも歴史家なので、巻末の「謝辞」を読むと、どうもサピエンシップと呼ぶ研究チームがあって、多くの資料を収集し、テーマを調査して著者に報告し、校正までしていたようです。ハラリ氏も「数え切れないほどの間違いや思い違いを正してくれた」と書くほどですから、著者は、どこか、新聞の調査報道チームのデスクか、週刊誌のアンカーマンに見えてきてしまいました。要するに、ハラリ氏は、たった一人でこの本を全て書き上げたわけではなかったと想像されるのです。それほど複雑な題材を扱っていますからね。
私の個人的見解では、著者のハラリ氏はどうもAI革命の将来を楽観していないように見えます。むしろ、悲観的です。AIのことを「人工知能」(Artificial Intelligence)ではなく、「人間のものとは異質の知能」(Alien Intelligence)の頭文字と考える方がいいかもしれない、と本音を漏らすからです。今や、AIは、製作した人間が想像もつかなかったことを自分の意志で?勝手に働き、人類による制御不能の何十歩か手前に来ています。そのうち、スタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅」に出てきたコンピュータHAL9000のように暴走しかねません。
フェイスブックの責任
この本で、最も印象に残った話は、フェイスブックにまつわる話です。フェイスブックは、宣伝広告収入を増やすためにユーザーエンゲージメント(テレビの視聴率みたいなものか)の増大を図り、「憤慨や憎悪を煽って攻撃的な言動に走らせる」ようなコンテンツがエンゲージメントを生み出すことを発見します。そこで、アルゴリズム(計算手順)を使って、そのようなコンテンツを拡散していったというのです。一番いい例が、2016~17年に、仏教徒が多いミャンマーで起きたイスラム教徒のロヒンギャ族に対する残虐行為です。仏僧のアシン・ウィラトゥという過激的な人物がフェイスブックに投稿した反ロヒンギャの煽動的なメッセージが拡散したことが原因だったと著者は断罪しています。ハラリ氏は「最大の責任は、ウィラトゥやミャンマー軍幹部などにあるが、責任の一部は、フェイスブックのエンジニアや重役陣にもある。…だが、肝心なのは、アルゴリズム自体にも責任がある点だ」と書くほどです。要するに、アルゴリズムはもはや人間の手に負えないほど暴走しているということなのでしょう。
何をしでかすか分からないAI
訳者の柴田裕之氏も「訳者解説」の中で、「AIは、人間の心の弱点や偏見や依存性に超人的な効率でつけ込む方法を知ったら、何をしでかすか知れたものではない」と書いております。
AI革命という「パンドラの箱」を開けてしまった以上、人類はもう後戻りできないことでしょう。この本を読んだ多くの人が、将来、ディストピア(暗黒世界)にならないよう、対策を考え、監視し、悪用されないよう何か手立てを打たなければならないと思うことでしょう。この本は、人々をそういった行動に走らせる凄い本だと思います。人類を破滅させないためにも読むべき本だと思います。
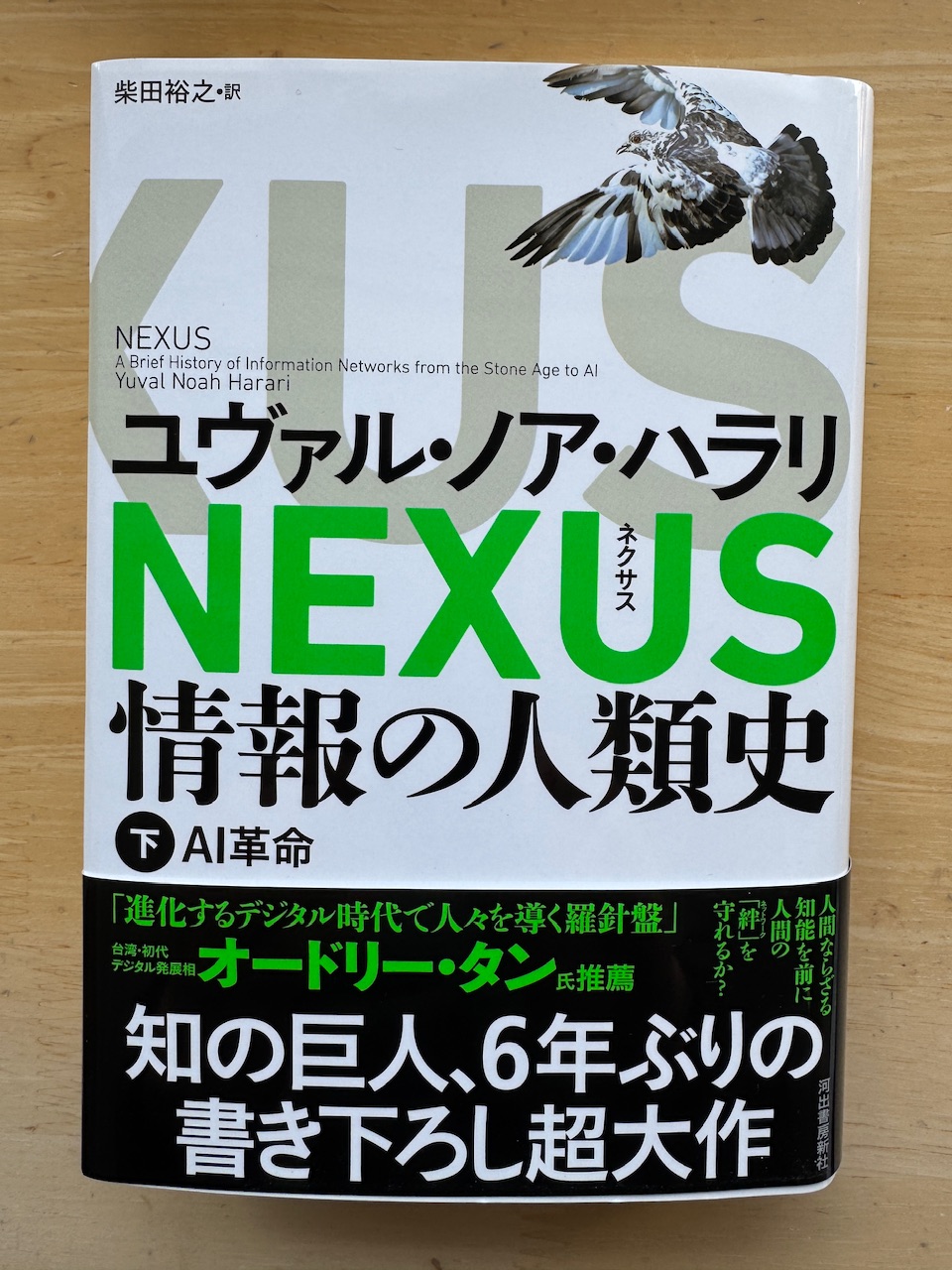
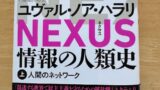


コメント